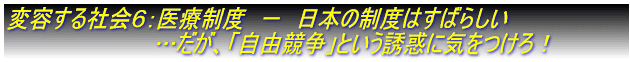
「日本の病院、今と昔」わたしは昭和25年にはじめて日本へやって来た。その頃の日本は決して清潔な国とは言えなかった。路上にはゴミが散らかっており、電車やバスの乗客は勝手にゴミを捨てていた。病院の看護には限界があり、入院患者の食事や身の回りの世話などは家族もしくは誰かを頼んで行なわなければならなかったのだが、泊まりで看病する人は病人のベッドのそばの床の上に布団を敷いて睡眠をとった。 衛生面はどちらかというと標準以下だった。とりわけ個人病院はひどかった。当時暮らしていた西宮市の近所の診療所の診療室の不潔さは、いま思い出しても嫌悪感がこみあげてくる。どの患者が使ったのかわからない汚れた包帯が床に放置されていた。
日本の病院の、とりわけ衛生度や効率の良さは賞賛に値するといえよう。順番を待つ時間が長いことは別として、外来患者や入院患者へ対する対応は迅速だし、東京都内の某病院でわたし自身が体験した限りでは、看護師たちの質の高さは特筆にあたいする。つまり日本の医療制度は医療機関としても、また規律ある公共制度としても比類なき成功をおさめているといえよう。この成功は伝統的な日本の一面というよりも、戦後の民主主義によって遂行されたことは明らかであろう。 「患者に医療費を負担させよ」さて、このような日本に比べ、イギリスはどうだろうか。
どちらも先進国でありながら、なぜこんなに違うのか。 イギリスだけではなく他のヨーロッパ諸国は多くの移民を抱えているゆえ、日本のように均一なサービスを提供することは不可能であると言っても差し支えないだろう。また公共の医療現場で働く人たちの勤労意識もヨーロッパに比べると日本の方がはるかに高い。 しかしそれよりも、財務上の理由もあるのだ。 イギリスの国民健康保険(National Health Service, 通常NHSと呼ばれている)は税金を財源にしており、利用者は収入に関係なく無料で治療を受けることができる。一方、日本の医療保険制度は収入によって負担する保険料が決定され、それを財源に成り立っている。さらに医療機関を利用するたびに自己負担として一割、二割、三割なりの費用を支払うことになっている。それにもかかわらず、日本では医者にかかる回数は一人あたり年間16回が平均的な数値で、これは先進国(OECD)30か国の平均6.6に比べると高い。入院日数も日本は平均31.5日で30か国のなかではトップだ(ちなみに平均日数は8.2日)。かえって日本ではこのような長期入院が「社会的入院」として問題視されている。 患者が医療費の一部を負担するという制度は健全だと思う。イギリスのNHSに比べても日本の制度の方が良い。所得に関係なく誰もが無料で医療サービスを受けることができるというのでは、結果的に医療現場にしわ寄せがくるからだ。 「公共の場に民間企業を招くな」
ちょっと話は逸れるが、極端な例を紹介しよう。 最近の「ワシントン・ポスト紙」に掲載されていたUSAirの記事だ(2007年10月17日付デイリー・ヨミウリ紙に全記事が掲載されている)。格安フライトを提供するこのアメリカの航空会社は意図的にすべてのフライトをオーバーブッキング(定員以上の予約をいれる行為)している。つまり飛行機代を支払いフライトの確認を済ませた乗客にも「チェックインに遅れた」ことを理由に、フライトを拒否することを常習的に行なっているわけだ。文句を言い、大騒ぎする乗客は警官に連行されるという。最近、フライトを拒否され取り乱した女性がベンチに縛りつけられ、後に死亡するという「事件」が起きた。チェーンが首を絞め、窒息死したらしい。この航空会社の社員たちは、不満と苛立ちをあらわにする乗客を相手にしなければならないので、オーバーブッキングなどしたくないという。それでも昨年の収益11億5千6百万ドルのうちの10億ドルがオーバーブッキングによる売り上げだったという。つまり明らかにこれは利潤と株主価値のみを目的とした経営による悲劇といえよう。
これはあくまでも例外的なうえ、日本では信じられないような話であろう。わたしが強調したいのは、民間であるかぎりは利用者より資本、市場、ひいては株主や利益へおもねる傾向が強くなるということだ。 いかなる政治/経済システムの社会においても、基本的な公共サービスをしっかりと監視することは常に必要であるといえよう。 (平成19年10月31日 原文は英語。溝口広美訳) |
© 2007 ハンス・ブリンクマン/溝口広美
 あれから50年が過ぎ、日本は変った。公共のスペースの清潔さには感心する。電車の車内、公民館や学校や美術館、博物館などは清掃がゆきとどき、デパートやショッピングアーケード内もピカピカだ。道路にもゴミなどなく、よく手入れされている。犬のフンもビールの空き缶も見当たらない。1995年の春に起きたオウム真理教による地下鉄サリン事件以来、駅や街角からゴミ箱が撤去されてもそうした清潔さは変らない。
あれから50年が過ぎ、日本は変った。公共のスペースの清潔さには感心する。電車の車内、公民館や学校や美術館、博物館などは清掃がゆきとどき、デパートやショッピングアーケード内もピカピカだ。道路にもゴミなどなく、よく手入れされている。犬のフンもビールの空き缶も見当たらない。1995年の春に起きたオウム真理教による地下鉄サリン事件以来、駅や街角からゴミ箱が撤去されてもそうした清潔さは変らない。 深刻な病気の治療のための手術ですら、命に別状をきたさないと判断されれば何か月も順番を待たなければならない。専門医に診てもらうための予約を取るだけで何週間もかかることもある。自費でプライベートの医療コンサルタントの所へ行けば100ポンド(約2万5千円)以下ということは稀であるうえ、あくまでもこれは診断というより相談であり、検査や薬の処方にかかる代金は別に請求される。衛生面に関してはまずまずといったところだが、ロンドンの大手病院の裏がかなり不潔であることをこの目で見たことがある。今の日本では有り得ないだろう。
深刻な病気の治療のための手術ですら、命に別状をきたさないと判断されれば何か月も順番を待たなければならない。専門医に診てもらうための予約を取るだけで何週間もかかることもある。自費でプライベートの医療コンサルタントの所へ行けば100ポンド(約2万5千円)以下ということは稀であるうえ、あくまでもこれは診断というより相談であり、検査や薬の処方にかかる代金は別に請求される。衛生面に関してはまずまずといったところだが、ロンドンの大手病院の裏がかなり不潔であることをこの目で見たことがある。今の日本では有り得ないだろう。
 前回のこのコラムで述べたように、日本では公共交通機関における民営化が起っても質を低下させることなくサービスを提供することができることを証明している。イギリスでも民営化がすべて悪いというわけではない。いつの日か日本の医療保険制度が利潤にもとづく決定にゆだねられるということもありえない話ではない。医療制度が民営化され、国民の健康より株主価値や時価総額を優先するなど、想像するだけでも身震いがする。
前回のこのコラムで述べたように、日本では公共交通機関における民営化が起っても質を低下させることなくサービスを提供することができることを証明している。イギリスでも民営化がすべて悪いというわけではない。いつの日か日本の医療保険制度が利潤にもとづく決定にゆだねられるということもありえない話ではない。医療制度が民営化され、国民の健康より株主価値や時価総額を優先するなど、想像するだけでも身震いがする。