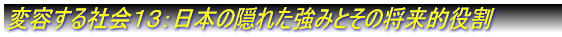
 金融危機の最たる原因とは? 金融危機の最たる原因とは?
金融関係のブログではないが、世界における金融および経済危機に関する膨大な記事、分析、コメントを読みながら、わたしも自分の見解を述べてみたくなった。ただし日本の状況のみにとどめたい。39年間の銀行員としてのキャリア(そのうちの24年間は日本だった)に加え、5年前から日本で暮らしているわたしの個人的意見は以下のとおりだ。
まず今回の金融危機の背景について。ベアー・スターンズやリーマン・ブラザーズといったウォール街の大手投資銀行が次々と倒産したのは、単なる金融システムの一時的な機能不全というわけではなさそうだ。これは「病」で、根は深い。つまりアメリカ社会にまん延する「病」なのだ。「米国経済の根幹は健全だ!」− 共和党上院議員ジョン・マッケイン大統領候補のこのセリフは、銀行がドミノのように次々と倒れてゆくただ中で発言されたのだが、「健全」どころか徹底的に腐っているといえよう。金融セクターだけの話ではない。ウォール街のいわゆる「銀行員」たちによる愚かしきデリバティブや貸付の数々が、システムを転覆させたことは確かではあるが…。
 イラク戦争をはじめたこと、地球温暖化を認めようとしない態度、執拗に「デモクラシー」の喧伝をする一方で弾圧政治を行なう国々と取引きをしている皮肉な事実、公的健康保険がないこと、主要なインフラに欠けていることなど、少なくとも過去8年間のブッシュ政権の大失策にも責任はある。 イラク戦争をはじめたこと、地球温暖化を認めようとしない態度、執拗に「デモクラシー」の喧伝をする一方で弾圧政治を行なう国々と取引きをしている皮肉な事実、公的健康保険がないこと、主要なインフラに欠けていることなど、少なくとも過去8年間のブッシュ政権の大失策にも責任はある。
さらに、不健康な食生活 - 人口の半分以上が太り過ぎ、そのさらに半分は肥満である - に加え、銃を所持する権利を認め、貯蓄もないのに返済不可能なほどの借金をつくって、住宅やモノを購入する無責任な消費パターンを続けてきた。
アメリカの複合的な病が痛痛しいほど明らかだ
もちろん今回の金融危機はアメリカだけが悪いわけではない。英国もアメリカの悪い部分を多いに真似したし、ヨーロッパ諸国もおおむねそうだった。
 日本はどうか? 日本はどうか?
アメリカに比べると日本の現在の金融と社会の状況は、前述したような「病」のどれにもかかっていないと言っても過言ではない。ただし、日本もいろいろな問題に直面している。少子化問題、近隣諸国との歴史問題をめぐるあつれき、教育の質の低下、政府がかかえている巨額の借金、中国や韓国などが台頭する一方でいまだに輸出中心の製造業に頼っている産業構造など。これからもこうした問題について、国の指導者たちは真剣に取り組まねばならない。
しかし今のところ、日本の隠れた強みは明らかだ。20年前のバブル崩壊から見事に立ち直ったのだ。株と土地の価値が急激に下落し、それから時間をかけて、痛みをともないながら景気回復をおこなった。1970年代半ばから80年代後半までが浪費の時代だとしたら、バブル崩壊後はほとんどの日本人が思慮分別のある消費を心がけるようになったといえる。そのおかげで現在の日本は正気を保っている国という観がする。混迷した90年代の呪縛から解き放たれ、自分の意見を発言しようという大胆さを見せる日本の指導者たちが現れてきた。
● 麻生首相がG8およびその他の国とともに緊急の金融サミット(首脳会合)を開くことを提案した。これは彼とブッシュ大統領の間で合意の結果のものだったという。
● 日本は、今回のアメリカのサブプライムローンによって膨らんだ不良資産の試算を手伝うため、90年代の金融建て直しを経験した会計士や法律家をアメリカへ送ることを申し出ている。
● アメリカが北朝鮮をテロ指定から解除したことに対し、日本は不満を表明。拉致された日本人を北朝鮮が公表するまで支援は再開しないとした。
さらに、金融市場では矛盾に満ちた、驚くような状況が展開している。ニューヨークやロンドン同様、日経平均株価も下落が続く中、円高に拍車がかかっているのだ。
アメリカの不景気を懸念し、日本の輸出業、とくに自動車産業や製造業全般が痛手を受け景気が低迷するという予測から、株価が下落しているにちがいない。不安とパニックから、銀行への貯金、債券買い、さらに外国投資を自国へ戻す転換が起きており、とくに最後の動きは円高を招いている。円の価値はドルと同様、こうした危機的状況においては安全だという信頼を得ていることは明らかだ。
世界を動かすアメリカを助けるにちがいない限られた国の一国として、日本がゆっくりと浮上してきている。アメリカの終焉という予想は、まだ早計だと思う。ただ、共生と協力を土台とする、複数の柱から構成される世界へと変わりつつある動きは感じられる。
 日本の新たな役割のためには、大きな変化が必要だ。おそらく戦後の日本以上に社会が変らなくてはならないだろう。居心地よく、時にはうぬぼれの強い島国日本は国際強調主義の国家にならなければならない。それは政治の土壌を変えることを強いるだろう。世界のあらゆる場で指導力を発揮し、国境を越えて巧みにコミュニケーションを駆使できる人材を輩出するため、今の教育を考え直さなくてはならないだろう。つまり、日本のためにも世界のためにも、従来の「危うきに近寄らず」という態度から、もっと積極的な参加型のスタンスへと変って行かなければならないのだ。 日本の新たな役割のためには、大きな変化が必要だ。おそらく戦後の日本以上に社会が変らなくてはならないだろう。居心地よく、時にはうぬぼれの強い島国日本は国際強調主義の国家にならなければならない。それは政治の土壌を変えることを強いるだろう。世界のあらゆる場で指導力を発揮し、国境を越えて巧みにコミュニケーションを駆使できる人材を輩出するため、今の教育を考え直さなくてはならないだろう。つまり、日本のためにも世界のためにも、従来の「危うきに近寄らず」という態度から、もっと積極的な参加型のスタンスへと変って行かなければならないのだ。
時間はかかるかもしれない。だがそうした変化は始まっているのだ。後戻りはできない。
(平成20年10月30日 溝口広美訳) |