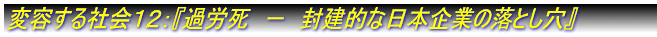
 わたしの心配… わたしの心配…
日本人の女友達の悩みを聞かされながら、サラリーマンの過酷な労働状態について改めて考えさせられた。まだ30歳にもならない婚約者が胃痛、頭痛を含む深刻な健康不良を訴えているという。その原因はというと明らかに連日の残業だ。毎晩10時まで、あるいはもっと遅くまで働かされ、毎月100時間以上は残業をしているという。その週末は、彼女がわたしに彼を紹介する予定だったが、ひどい頭痛のため彼は直前になって約束をキャンセルした。
あまりにも気の毒な話だ。わたしは彼女に婚約者は転職をするべきだと説得した。超過残業と無縁の会社が日本にもあるはずだ。これは彼の健康だけではなく生命にかかわる問題なのだ。最近たまたま過労死のニュースを続けて知ったので、彼女に事の重大さを諭した。過労死とは、十分な休息も取らず夜中まで長時間オフィスで働かされる結果、過度のストレスや鬱病や疲労に悩まされ、突然死することをさす。過労死による死亡者数は年間100人を超すといわれている。しかも女性も含まれている。
 日本では会社や仕事が優先で、多くの人たちが自分の家族や個人の趣味や余暇の時間をないがしろにするといわれている。健康でさえ後回しのため、ストレスによる胃痛や頭痛は日本の会社社会では欠かせぬものとして昔から言われてきたし、55年も前に日本で銀行員として働いていたわたし自身も、ストレスから生じる体調不良に悩まされたものだった(ただし、日本人の上司ではなくオランダ人上司のもとで働いていたのだが…)。 日本では会社や仕事が優先で、多くの人たちが自分の家族や個人の趣味や余暇の時間をないがしろにするといわれている。健康でさえ後回しのため、ストレスによる胃痛や頭痛は日本の会社社会では欠かせぬものとして昔から言われてきたし、55年も前に日本で銀行員として働いていたわたし自身も、ストレスから生じる体調不良に悩まされたものだった(ただし、日本人の上司ではなくオランダ人上司のもとで働いていたのだが…)。
しかし過労死はまったく別の次元の問題だ。
1990年代の初めにバブル経済が崩壊、90年代のグローバル化する世界経済を背景に競争力を高める日本企業の現場でこのような悲惨な突然死が生じているとは驚くべき話だ。終身雇用という保証がなくなり、職場ではリストラによる人員減らしが行われ、その結果限られた社員数で相当の仕事量をこなさなければならなくなった。リストラは避けられないものとみなされたが、日本経済が修正軌道をしたといわれる2002年以降になってもひとりひとりに課される仕事量は軽減されるどころか増える一方のようだ。
このような状況に対し、企業側は「先行き不透明な現状」において「中国経済が日本を脅かし」、今後も「経費節減」は不可欠だからやむを得ないと言う。だが、実際のところ世界に名だたる日本の大企業の中にはこうした理由を利用して過労死を招いているわけである。
 サービス残業の非をあばく サービス残業の非をあばく
誰も「サービス残業」のなんたるかを知らぬわけがない。食事も休憩もとらず、仕事が終わるまで職場を離れることができない。帰宅途中で、そばやうどんを食べたりコンビニストアでインスタント食品を買い求め、遅い夕食を済ませる。雇用主から正規の賃金が払われない賃金不払残業は労働者の健康を害し、労働者を搾取しているといえよう。
日本の会社社会で温存され、奨励されてきた封建的なしきたりなので、誰もなにもできないようだ。ところが、1980年代後半に政府が過労死を労災申請の対象として認めて以来、遺族は労働基準監督署に労災補償給付を求めて申請を行うが、認められるのは半分程度らしい。そこで裁判所へ提訴するケースが増えてきた。
例えば、2002年にトヨタ自動車の男性社員(当時30歳)が突然死したケース。会社側は彼の死の直前の労働時間は月38時間だけだったので直接の因果関係を認めようとしなかった。ところが、実際は月144時間と言う過酷な残業をこなしていたことが証明されると、それは「自己研磨」のための自主的労働だと主張。男性の妻は訴訟を起こし、2007年に名古屋地裁は遺族側の主張をほぼ認めた。トヨタ側からは何のコメントも表明されなかった。
会社のマネジメントを向上させれば少なくとも過剰労働は防げるとも言われている。日本で暮らしている誰もが、日本ではミスを犯さないよう確認、再確認、再々確認がなされ、そのために効率が悪いことは承知している。しかもこのせいで、個人レベルでの判断基準は強化されるどころか、弱まるばかりだ。
今でも世界第二位の経済力を誇る日本は、しばしばアジア諸国にとってお手本とみなされている。しかし日本企業が産休制度や育児支援なども含め総合的に雇用制度を再検討せず現状のままでいたら、いつまでたっても「上質な暮らし」や「職場における安全性」といった分野で他の先進諸国に大きく水をあけられてしまうにちがいない。
(平成20年9月30日 溝口広美訳)
|