|
***12月*** 12月5日 お堂でジャズ 「大聖堂でヘンデル、教会でバッハ、それなら寺のお堂でデュークエリントンもよかろう」− オランダのリード五重奏団カレファックス(Calefax)をゲストに迎えた時、三田の魚藍寺のご住職はきっとこう思ったにちがいない。 オランダの友人から誘われて魚藍寺でのジャズコンサートに出かけてみた。靴を脱ぎ、脱いだ靴を棚に収め、お金を払い(この夜は拝観料ではなくチャリティー寄金だった)、ひそひそ声で話し、お香とお供え物で埋め尽くされた祭壇の前を静かに素早くすり足で進み、畳の部屋に配列された仮設の椅子に座るところまでは、どこの寺でも起こりえることだ。本堂はいつの間にか50〜60人もの人でいっぱいとなり、低い天井と華麗な天蓋と威厳あふれる仏像を背景に、木管と金管楽器を手にした長身のオランダ人の奏者5人がどんな演奏を聞かせてくれるのだろうかと会場内は期待を寄せていた。
コンサートが終わると、ちょっと困ったことが起きた。5人の奏者はまだ夕食を食べていないという。エージェントは帰ってしまった。魚藍寺界隈は繁華街とはほど遠い閑静な住宅地だ。助け舟のつもりで、わたしは品川にあるフランス風カフェはどうだろうかと言うと、そこはタクシーで移動しなければならないうえ、楽団員たちの予算ではあまり贅沢ができないと誰かが耳元でささやいた。 もっと安くて、できれば日本食を食べさせてくれる所はないか。うなぎ屋を思い出した。ここから歩ける距離だ。それに、うなぎの燻製はオランダ人の大好物だ。「うなぎ以外にもなにか食べられるのか?」うなぎ屋はうなぎしかない。 それでは寿司はどうか。バスで移動できる。即、決定した。楽器を担いだ楽団員と友人たちは疑いもせず、わたしの後をついてきた。バス乗車はちょっとした冒険ですらあった。初めて訪れた日本で体験するバスの切符の清算だ。オランダと違い、両替も支払も自動なので操作にまごついた。時間がかかったのは仕方がない。11人の集団だ。この夜、都内のバスに遅れが生じたのはこういう理由だったわけだ。 それでは寿司はどうか。バスで移動できる。即、決定した。楽器を担いだ楽団員と友人たちは疑いもせず、わたしの後をついてきた。バス乗車はちょっとした冒険ですらあった。初めて訪れた日本で体験するバスの切符の清算だ。オランダと違い、両替も支払も自動なので操作にまごついた。時間がかかったのは仕方がない。11人の集団だ。この夜、都内のバスに遅れが生じたのはこういう理由だったわけだ。 翌日の夜は東京オペラシティーのリサイタルホールで演奏をしたカラファックス。来年も日本へやって来るという。ぜひ出かけてみてください! 12月10日 創立150年
緑豊かな三田キャンパスはわたしの住まいのすぐそばだ。キャンパスを通って田町駅へ行くこともある。2週間ほど前、大学祭へ友人を連れて行った。キャンパス内には食べ物屋が並び、賑やかで活気にあふれていたのはきっと150周年ということも関係していたのかもしれない。 義父は慶応大学出身だった。1927年の卒業生だ。わたしは彼の所持品だったペン先のロゴがついた慶応のカフスを今も愛用している。 たまに学食でお昼を食べることもあるが、学生たちは特にわたしの存在を気に留めることもなく、むしろきっと教員と思っているのかもしれない。大きな壁画のある、素敵な学食だ。先月その壁画が消えた。塗りつぶされたのかと勘違いし、立腹のあまり電話で問い合わせてみると耐震性強化工事のため「一時的にはずした」ということだった。
12月20日 日本とオランダの合作 二人の友達を夕食に招いた。手料理でもてなそうと思い冷蔵庫を開けてみると、あると思っていた食材がないではないか。あるのはゴーダチーズ、ハム、レンコン、いんげん、グリーンピース、それからお米。 困ったと思った途端ひらめいた。半世紀前も昔に妻が似たような窮地にたたされ、即席でチーズとハムと玉ねぎを角切りにし、米と一緒に炊飯器で炊きこんだ。味付けは塩とコショウだったと思う。「チーズご飯」と名付けた。オランダと日本の合作料理で、シンプルだが誰も作ったことのない食事で何と言ってもとてもおいしい。昭和36年の毎日新聞でも掲載されたことのあるレシピだ。 そこでわたしもチーズご飯を作ることにした。レンコンは思いがけない発見だったがチーズの味がきわだった。コートド ローヌ ヴィラージュの赤ワインのおかげで低地オランダの味も盛り上がった。(フランス語ではオランダを「低地域」と呼ぶのをご存じですか) ***11月*** 11月12日 関ヶ原の大砲
何気なく尋ねた質問のおかげで、予想もしなかった任務をこなすことになり、そこで意外な発見をすることとなった。 日蘭協会の例会で某婦人と話をした時、1600年4月、日本に漂流した最初のオランダ商船リーフデ号の船尾についていたエラスムス立像の行方について聞いてみた。かれこれ40年ほど前に東京国立博物館で開催された仏像の展覧会のような場で、わたしはその立像を見たことがあった。東京からそれほど遠くない場所にあるお寺でそれは発見されたという話だったが、はっきりとは覚えていない。
日蘭協会の女性部会の幹部でもある某婦人は、彼女のみならず会員たちもこの話を聞いたことがないが、興味深いと言い出し、博物館へ問い合わせてみると約束した。するとどうもこのエラスムス立像が短期間ではあるが一般公開されることとなり、ついてはわたしがこの像についての話を女性部会のために行えないだろうかと、某婦人からお願いされた。 わたしは自分が歴史家でも海事専門家でもないから無理だと断ったのだが、女性部会の会長はそれでもいいからと言ってくれたので、さっそく蔵書をひっぱりだし、ロッテルダムの海事博物館やオランダのしかるべき機関に問い合わせ、さらにインターネット情報で補足しながら調査をすすめた。数週間のうちに、わたしもすっかり「にわか専門家」となり、講演当日の今日は、得意げな顔で会場へ出かけた。聴衆の中には歴史書を持参してきている人もいて、わたしの説とまったく違うことが書いてあったらどうしようかと思ったが、気を取り直し、2年間にわたるリーフデ号の航海のドラマを説明した。ロッテルダム港から5隻の船が出航したものの、日本の九州に漂流したリーフデ号だけが航海を成し遂げた船だった(残りの4隻は航海途中で難破または航海を断念)。110人の乗組員のうち生存者は24人で、その中にはウィリアム・アダムス(三浦按針)とヤン・ヨーステン(のちに家康から土地を与えられた彼は、そこを「八重洲」と名付けた)がいた。家康はリーフデ号の19の大砲を押収し、それらを関ヶ原の戦いで使用したと言い伝えられている。
重要文化財として指定されたエラスムス立像は、最初の日蘭交流を物語る唯一現存する物証として展示され、再び博物館の薄暗い倉庫へと戻って行った。好奇心あふれる誰かがこの立像についての問い合わせをし、学芸員が展示を決定するまで、しばらくお役目御免ということだ。 (「リーフデ=慈悲/博愛」という意味の商船の船尾に飾られていたエラスムス立像の行方については話が長くなるので、ご興味のある方はぜひメールでお問い合わせください。講義の内容のコピーを送信します。) 11月22日 箱根は大賑わい オランダから遊びに来ている友人を連れて、箱根の温泉へ一泊旅行をしてきた。強羅にある「環翠楼」という旅館に泊まった。昭和の面影を残す小ぎれいな旅館だった。もともとそこの建物は三菱財閥岩崎家の別荘だったが、終戦から4年後に現在の旅館主が譲り受けたという。森閑とした日本庭園や梁や柱などの内装を見れば、なるほど歴史の重みを感じる。ちょうど紅葉の時期だったので、庭園の木々は鮮やかな朱色に染まっていた。家具や寝具などはどういうわけか使い勝手もサイズも昭和のままで、仲居さんも控え目だったので、まさに伝統的な旅館の極みという感がした。
ところが、36時間の箱根温泉旅行の中で静寂を楽しんだのはこの旅館に泊まった時だけだった。どこに行っても人ごみと長い行列に遭遇し、しかも大半は韓国と中国からの観光客だった。硫黄の噴煙を噴いている、おどろおどろしい大涌谷にも人の群れが途切れることがなかった。
「これで不況?」と友人が驚いていたが、本当にそうだ。箱根のホテルも旅館も新年まで予約でいっぱいだ。小田急ロマンスカーを利用し新宿に到着すると、どこのカフェもレストランも賑わっており、中には順番待ちの列ができている場所もあった。銀座、表参道、渋谷、浅草、上野公園といった都内の人気エリアなどへ出かけると、人の数は減少傾向にあるというより、確実に増加している。おそらく買い物は控えているのかもしれないが、家にいるより街へ出かける人がいることは確かだ。
タクシーに乗ると、運転手さんは会社を退職しタクシーの運転手になったと話し始めた。「日本の経済は大丈夫だと思いますよ。企業は金を持ってますし、個人も消費できる金があるからね。」と彼は朗らかに言っていた。 11月25日 100年前のハガキ − 続き
宛名は秋田市の大山重綱様、日付は明治40年2月3日。「あづま美人其十六」と印刷されているので、おそらくシリーズものの葉書だったのだろう。 鶴舞千歳樹 この漢文の意味は「鶴は千載の樹に舞い、亀は万年の池に遊ぶ」ということで、長寿と福を祝う詞だ。
「一昨夕雨のうちに東京を出て、昨日この地にはいる。???君(達筆すぎて判読不可能)に昨日面会。久し振りに快談。これからさらに…西行」 差出人はまるで西行法師気どりだ。葉書の写真の農夫から西行を連想したのか。とにかく西行法師の時代には「東京」という地は存在しなかったのは確かだ。 ***10月*** 10月10日 オランダ人も怒ってます! 「変容する社会11」で、とくに東京都内のフレンチとイタリアンレストラン事情を論じた。その時の結論のひとつとして、値段が高いからおいしいとはかぎらないと述べた。 実は昨晩、レストランではなく居酒屋で、同じような教訓を学んだ。赤坂にあるジパングというモダンな内装の居酒屋でお客をもてなすために、個室を利用した。個室といってもオープンで、賑やかな店内の雰囲気が楽しめるようになっている。食事は和/洋風の一品料理が中心で、これなら予算内で楽しめるだろうと思っていた。 ところが、料理にがっかりした上、量は少なく、値段はとんでもなく高い。脂身の部分が多いサーロインステーキ100グラムは一皿4、800円也。紙ほどに薄くスライスされた数切れのチーズプレートは1、800円也。炭火焼きの焼き鳥はよく調理されていなかったし、スープは飲める代物ではなかった。ご飯やデザートやコーヒーは注文しなかったにもかかわらず、渡された伝票を見たらなんと5人で89、281円也(5、000円のルームチャージ込み)。ビール5杯とワイン3本(しかもごく普通のボトル)を除いても、あの食事だけで53、000円とはあまりではないか。満腹感などかけらもなく、怒りだけが込み上げてきたが、他のお客さんがいたのでぐっとこらえた。 伝票といっても合計金額だけを手書きしたものだ。つまり料亭でよく見かける伝票だ。内訳は明確ではない。この十年あまりの間に、料亭は洋風レストランやもっとカジュアルな和風の店にお客を奪われてしまった。 ジパングは料亭でもないし、高級そうな店でもない。サラリーマン向けの、飲んで食べれる気軽で賑やかな居酒屋だ。それなのになぜ料亭並の値段なのか。ふと伝票を見ると「なだ万」という文字を発見。なるほど、ご時世にあわせてこの老舗も、ホテルのレストランやデパ地下の惣菜売り場へと進出していることを思い出した。本性は隠せない。 しかし誤解しないでほしい。これはあくまでも稀な出来事だ。日本では、おおむね妥当な値段でおいしい食事ができるし、店や食事の種類も実に豊富だ。値段に見合った食事とサービスが約束されている。ただし、おそらく料亭や料亭もどきは例外なのだろう。 家に帰ってクレジットカードの明細を見たら、内訳が印刷されていたことに気がついたが、それでも後味の悪い気分は癒されなかった。 10月15日 100年前のハガキ 骨董の漆箱から30枚ほどの明治時代のハガキを見つけた。たしかはるか昔、ロンドンの古書店で購入したことを思い出した。半分は使用済みのハガキで、切手までついている。英語で書かれたものはおそらく、日本を訪れたか日本に暮らしていたイギリス人が、祖国の家族や友人へ送ったものだろう。日本語で書かれたハガキは日本人から日本人へのものだ。日付はどれも1910年代だ。 関西に住む、写真家かつアンティークハガキ蒐集家の友人曰く、歴史的価値のあるものもあるし、ないにしても興味深い。
「親愛なるグレーシー。お便り、およびイースター祭の予定をいただきどうもありがとう。イースターまであと数日です。(天意にかなえば)皆に会えることでしょう。」 差し出し人は「いとこのM.V.」と記されている。さらに「予期」という追伸には「わたしたちも間もなく、この娘さんたちとそっくりになることでしょう。そう思いませんか。この日本の葉書、お気に召されて?」 まさにヴィクトリア時代だ。ジェーン・オースティンの世界そのものだ。
「これをご覧になると、芸者が弾く三味線というものがどういう楽器かおわかりになるかと存じます。この少女は単なる流しの三味線弾きです。芸者と勘違いなさってはなりません。」 GDからGDへの厳しい戒めということか。 来月は日本語のハガキを紹介します。 10月24日 午後5時のメロディーinトウキョウ 午後5時になった。子どもに帰宅の時間を知らせるメロディーが、東京中でどこからともなく聞こえて来る。アナウンスではなく懐かしい童謡のメロディーだ。明治時代から歌い継がれてきた童謡は日本人なら誰でも知っている。 夕焼け小焼けで日が暮れて
『夕焼け小焼け』のメロディーだけが毎日午後5時に流れて来る。不思議なもので曲を聞いただけで、自然に歌詞も思い浮かんで来る。 それにしても「からすと一緒にかえりましょ」とは!今ではからすは都会の厄介者だ。ゴミ袋を破る、小動物や鳥を攻撃する、鳴き声はやかましい。 童謡では、からすは人間の仲間だったのに、時代は変った。 ***8・9月*** 8月13日 写真展の準備 ヨーロッパで一か月間過ごした後、日本へ戻ってきた。休暇のつもりだったが、写真展の準備におわれ忙しかった。8月29日から東京都内で開催予定の写真展では、わたしと友人エイスブラント・ロッへが50年ほど前に撮影した写真を展示するので、まずはネガを探すことから始まった。ネガが見つかるとスキャンをし、そのデータを東京の富士フイルムの担当者へ送信するわけだが、もちろん写真のキャプションを添えなくてはならない。ふだんは根気強い翻訳家の溝口広美さんも、今回は堪忍袋の緒が切れそうだった。 エイスブラントのネガは、アムステルダムにある彼の自宅の地下室に置いてある箱に保管されていた。博物館のようなオタク族の蟄居のような彼の風変わりな家の中は、世界でも珍しいヴィンテージの映写機のコレクションや、額に飾られた大きな写真、その他いろいろなモノにあふれ、居間の片隅には何台ものコンピューター機器が置いてある。そこから彼はインターネットを駆使して世界中に自分をアピールしているのだ。 わたしの古い写真はというと、ロンドンのノースアクトン付近のA40(自動車道)沿いにある貸倉庫に保管してある茶箱に保管されており、二人の友人の手を借りて、山積みにされた荷物のなかからその古い茶箱を見つけ出した。 ところで、今回のロンドン−東京間はヴァージン航空のプレミアムエコノミークラスを利用した。このサービスはなぜか他の航空会社にはないようだ。長距離のフライトを快適に過ごしたいからエコノミークラスより高い運賃を払うのは構わないが、ビジネスクラスは高すぎるので躊躇したいという旅行者にふさわしい。大きめの椅子や広めの足元のスペース、静かな機内。無造作に席をあてがわれたエコノミークラスとは一味違う。 将来はこうしたプレミアムエコノミーが国際線における「平均的」なサービスとなることを望みたい。 8月23日 さらなる写真展の準備 日本に戻ってから一週間になるが、あいかわらず写真展の準備に追われている。富士フイルムの担当部署はプロ集団だが、それでもキャプションの細部のチェックのための連絡がはいる。撮影年、撮影場所、撮影者、詳細についての日本語と英語のテクストを作成し、それらはプロデューサーの厳密な審査をクリアしなければならない。「おそらく…だろう」などというあいまいな記述はご法度だ。 8月29日 写真展ついに開催
9月6日 昭和へタイムスリップ 亡妻の親戚で、85歳になるご婦人から夕食に呼ばれた。久しく訪ねていない彼女の所へ出かけてみたら、まさに昭和へ後戻り。昭和35年あたりの家族アルバムを開いているような気分になった。通された部屋は小さな畳の間。台所は狭く、流しもコンロも昔のままだ。部屋の隅には古びたテレビ、別の隅にはお仏壇。部屋の窓を開けると小さな庭の垣根越しに隣の家が見える。 「昭和そのものだね!」とわたしが言うと、ご婦人は「狭くてごめんなさい」と謝った。貧しくてこのような暮らしをしているのではなく、彼女はまったく「昭和の人」なのだ。これまでの生活様式に慣れ、気心の知れたご近所さんに囲まれ、小さな庭つきの小さな家で幸せに暮らしている。最近は若い人だけではなく彼女のような高齢者も高層ビルのマンションで暮らすようになったそうだが、庭もなく通りの様子も窓から見えず、近所づきあいもなく一人暮らしということがしばしばだ。ハイテクで快適な居住空間かもしれないが、あまりにも孤独すぎる。 このご婦人は昭和を懐かしがったりしない。彼女の中では、いまだに昭和は続いているのだ。 9月15日 満願!
「この本は、いかに昭和 − 特に戦後の昭和 − という時代が平和で成長に満ちた激動期であったかということを振り返るのと同時に、贅沢と奢侈にふける傾向が強まりバブル経済がはじけるまでそうした喧噪が止まらなかった様子を明瞭に描いている。日本暮らしの長い著者ハンス・ブリンクマンが考える、戦後の昭和とその時代が日本社会に残した遺産とはなにか。」 出版社のウェブサイトに載っている宣伝文句はこのようなものだ。 9月30日 写真展終わる
写真展のカタログを作成しなかったので、多くの人ががっかりしていた。 そこで、今度は写真集の出版だ。ああ、忙しい! ***7月*** 7月15日 ロンドンに戻ってみると… 東京からロンドンに戻ると、街のリズムに慣れるまでに時間がかかる。これは時差や公共サービスのよしあしに慣れるのとは少し違う。
ロンドンでは人の動作や態度が大雑把でぶっきらぼうで、時には店員ですら無作法だと感じることもしばしばだ。ウェストエンドという繁華街に出かけ、腹を立てて家に帰ることもある。それでも、ロンドンを歩いていると自由で多様な人生があるということを感じ、心が晴れる。東京ではいつも他人を気にし、きちんとしなければならないという心理的プレッシャーがかかり、あれもダメこれもダメと言われ、常に規則に従わなければならない。そのため東京ではなにをしても、どこに行っても窮屈に感じてしまう。 完璧な街ではないけど、ロンドンは人々に刺激と愉快な気分を約束してくれる。人ごみに飽きたら、気分転換に公園に立ち寄ってみると違った愉しみが待っている。広々とした緑豊かな空間で、昼寝をしたりピクニックをしたり読書をしながら夏のひと時をのんびりと過ごす。 東京は整然としており何事も「予想できる」街なので暮らしやすいが、多様な文化と言語と民族が混ざり合い、喧騒あふれるロンドンは決して飽きることはない。
7月19日 最新版の『逢びき』 今夜は友人と風変わりな舞台を見に行った。ノエル・カワード脚本、デビッド・リーン監督の悲恋映画『逢びき』(1945年)を現代風にアレンジしたものだ。駅の待合室での逢びきは原作にそったものだが、それに加え、歌やダンスやお笑いが手を替え品を替え繰り広げられる。 こういう舞台を見るたびに、ロンドンの演劇のせつない現実を痛感する。結局、まじめな舞台は人気がないのだ。大衆はミュージカルやエンターテイメントを求めてやまない。特に夏はその傾向がいっそう深まるようだ。 7月24日 アムステルダムでの運河下り
7月30日 古き良き時代のリゾートホテル − スイス編 この夏のハイライトはスイスへの旅行だ。1928年と48年の冬季オリンピック開催地であり、保養地として有名なサンモリッツから10キロほど離れた山の中腹にあるリゾートホテルへ宿泊した。
食事や施設やコンシェルジュの満足度はいうまでもない。しかしわたしが最も感心したのは、ホテル全体の静かな雰囲気だ。宿泊客の邪魔をせず、後を追いかけもせず、おしつけがましい態度も見せずに、こちらの要望を即座に理解し、対応してくれる。かなりの数のスタッフをかかえているのに、誰もが静かにホテル内を歩き、日本では必ず聞こえてくるBGMなど一切ない。音楽といえば、夕食の後にラウンジで演奏されるピアノとバイオリンとギターのアンサンブルぐらいだ。食事の時に飲み残した水やワインのボトルは、こちらが頼む前に若いウェイターが部屋番号をボトルに記し、次の食事の時に持ってきてくれる。「こちらでキープしておきましょうか?」「お客様のお部屋番号は?」などということを、いちいち確認などしない。 星の多いホテルほど、スタッフが目立ちたがり、こちらになにかと質問し、自分の存在をわからせようとするきらいがあるようだ。特にこれは日本のホテルに顕著だといえよう。こちらが頼みもしないのに、しかもたいして重要でもないような事ですら説明をし、確認をする。 スイスのリゾートホテルに泊まって改めて「最高のサービスとは相手にうるさくつきまとわないこと」であることを認識した。 ***6月*** 6月5日 なんという無駄使い! 「変容する社会」その9と10で述べたように、わたしたちは地球温暖化に取り組むための「行動」をおこさなければならないのだ。日々の暮らしの中で気がついたエネルギーの無駄使いはこんなにある。 その1 都バスの冷房は、外気の温度に関係なく、低く設定しすぎのようだ。乗った瞬間に上着をはおらないと寒くてかなわない。乗客が半分しか乗っていない場合でも、冷房は必要以上にききすぎている。 その2 最近、某病院に入院した時のこと。看護婦がわたしの部屋にやってくるたび、決まって電気をつける。部屋に太陽が気持よくふり注いでいる時など、電気はいらないと言ったのだが、そうすると看護婦は驚いたような表情でわたしを見ていた。
その4 最近、東京のタクシーに乗ると、くだらぬ装置を見かける。料金精算の時、「ただいまの料金は800円です」という声を発する精算機だ。メーターに800という数字が表示されているから言われなくてもわかるのに。それとも、タクシー運転手はしゃべるのも億劫というのか。 6月14日 がんじがらめの儀典 昨夜はわたしの所属する某友好団体の例会に出かけた。名誉総裁は秋篠宮殿下。ある程度の儀礼を表することはわかるが、わりとリラックスした集まりだったので、堅苦しいことはなかろうと思っていた。ところが、秋篠宮ご夫妻が会場へ入ってくる時と退場する時に、全員が起立し拍手をしなければならないだけではなく、ご夫妻が次の間へ移る際にも同じように起立と拍手をするよう事前に言い聞かされた。 こうした堅苦しさとは裏腹に、ご夫妻は意外にも気さくに人々と歓談していた。わたしも殿下と話をし、彼は気取りのない方だという印象を受けた。 おそらく儀式的なことを好む誰かが取り決めたセレモニーだったのかもしれない。わたしの隣にいたオランダ人は小声で、「うちの女王はうんざりするに違いないだろう」とささやいた。 6月15日 大阪での朗読会 大阪で自作の短編を読む機会に恵まれた。この集まりは2005年にトレーシー・スレーター(Tracy Slater)が米国ボストンで始めた文学クラブの一環として、大阪で行われた。わたしの他に3人の作家がゲストとして招かれ、それぞれ15分間自分の作品を朗読した。わたしの短編は時間内で読みきることができなかったが、おかげでどのようにして話が終わるのかということを知りたがった聴衆が本を買ってくれた。 
19世紀の文学サロンの雰囲気を21世紀らしい場所で再現するという点で、この「4つの話(英語ではFour Storiesと呼ぶ)」は粋な集まりだといえよう。大阪の会場は「ポルトガリア」という名前のビストロで、店長のエドアルドはおいしい料理を用意してくれた。また彼は聴衆と一緒に朗読に耳を傾け、わたしの本も買ってくれた。 朗読会が終わり帰ろうとすると、外は雨が降っていた。エドアルドは笑顔で「返さなくてもいいよ」と、不要になった傘を手渡してくれた。本がきっかけで結ばれる人の縁はいまだに健在だ。 6月26日 足の悩み 東京の街を歩きながらよく見かけるのは、若い女性の気の毒なほど曲った足だ。重症のO脚の女性もたまに見かける。近所の大学の女子学生の中にも、曲った足で歩く人がおり、見ていて気の毒だ。 どうしてこれほど気になるのかというと、あえて言わせてもらえば、そうした女性はだいたいヒールの高い靴をはいているのだ。女性のファッションに無知なわたしではない。だが、サイズの合わない靴や、歩きにくい靴をはいていれば、足の骨が曲がってしまうことだってありえるのだ。もし若い女性が、高いヒールの靴をはくことで魅力的に見えるという幻想を抱いているとしたら、わたしはこう言いたい - 靴をぱかぱかと鳴らしながら歩いている姿は、気の毒でもあり、見るに堪えない光景だ。 洋服やアクセサリーは自己イメージを作るために不可欠なアイテムだ。また女性にとって靴はもっとも重要なパーツである。しかし、見栄えをよくするために健康を害するようになったら、それは本末転倒な話だ。 普段は歩きやすい靴を履き、ヒールの高い靴は、夜に着飾って出かける時のためにとっておくというのはいかがだろうか。 ***5月*** 5月2日ー5月6日 ラ・フォル・ジュルネ in 東京 正月休みの後にやってくる大型連休といえばゴールデンウィーク。毎日12時間 ちかくオフィスで過ごすサラリーマンたちも、この時ばかりは家族と一緒に国内旅行や短期の海外旅行へ出かける。 わたしは東京国際フォーラムで開催された「ラ・フォル・ジュルネ(La Folle Journée)」で音楽を楽しんだ。日本語では「熱狂の日々」と宣伝されているが、それでは「気の狂った、気違いの、気が狂うほど興奮した」というfolleの意味が十分に表現つくされていない。実際には非常に「フランス的」なワイルドさが錯綜していた。たった45分間から60分間の短いコンサートが、6ヶ所の会場(最大で5000客席のホール)において朝から晩まで繰り広げられ、しかも入場料は手ごろな値段だ。
大規模な音楽会だとうんざりするなかれ。プログラムに目を通し、聴きたいコン サートのチケットを買ってしまえば簡単だ。わたしなど、ウェブサイトの英語のページはアクセスできず、プログラムもチケットセンターもすべて日本語のみだ ったにもかかわらず、その障害を越えてこのお祭りを楽しんだ。音楽だけではなく、会場では食事もできた。「大規模なイベント」だと感じなかったのは意外だ ったが、それはおそらく国際フォーラムのあの一種独特な建築効果によるのかもしれない。 もしゴールデンウィーク中に東京にいるのなら、「ラ・フォル・ジュルネ」へ出 かけてブルーな気分をふっとばしてみてはいかがでしょうか。 5月13日 日本アルプスへの旅 音楽会へ出かけた以外は仕事ばかりのゴールデンウィークだったので、山で息抜きをすることにした。 行き先は海抜1600メートルの上高地。半世紀ほど前に当時の銀行仲間と一緒に訪れたことがあるが、その記憶は朝もやのようにぼやけている。 新宿駅から約3時間ほどで松本駅に到着すると、今度はそこから在来線に乗り換 えて新島々駅へ移動。そこからさらにバスで上高地へ。次のバスの出発まで45分間も待たなくてはならない。しかも駅の周りには何もない…。
バスで上高地へ向う途中、土砂に埋まった脇道を見つけた。ぼんやりとした記憶が甦る。昔の旅の途中にこんなことがあった。土砂崩れが起きて道路が陥没し、一部は完全に崩れ落ちてしまった。わたしたちはバスから降ろされ、わずかに残された道路の残りの部分を、荷物を持ちながら歩かなければならなかった…。 あの時の場所ではないかと思った。たしかに見覚えがある。むき出しになった崖の斜面は今でも無気味で、最近も大規模な土砂崩れがあったと思われる。路上には土塊が残されたままだ。この道路は現在使われておらず、あきらかに危険この上ないスポットのようだ。 新島々駅から上高地への足はバスかタクシーのみで、自家用車の乗り入れは禁止 されている。そのおかげで新鮮な空気と自然の静寂を味わうことができる。この静けさを時折やぶるのは鶯の声と梓川のせせらぎだけだ。創業75周年を迎える 帝国ホテルとその他いくつかの宿泊施設があるだけで、あとはなにもない。喧噪と商業化された娯楽施設とショッピングを求める人間には魅力のない場所だろう。本格的な登山者である必要はない。かくいうわたしも山登りなどしない。自然の偉大さを堪能するだけで十分だ。 
5月15日 上高地の温泉 滞在しているホテルには温泉施設がないが、川向こうの旅館にはあるという。そこで今夜は温泉につかった後、その旅館内で夕食をとることにした。食事が終わり、いざホテルへ戻ろうと思ったが月の明かりすらない真っ暗な中、橋を渡り林を抜けて徒歩で帰れるだろうかと心配していたら、旅館の人が「歩いて帰れませんよ、真っ暗ですから。車を出しましょう」と言ってくれた。上高地は自然だけではなく、人も良い。 5月16日 バス停はトンネルの中(!?) 規律の厳しい日本でも楽しく掟を破ることができるのだ。 今日は乗鞍高原へ行くことにした。上高地から乗鞍高原まではバスで約1時間。 直通のバスはないので、途中で乗り換えなくてはならなかった。乗鞍高原では新緑の美しい白樺の径を歩いたり、ミズバショウを見に湿原へ出かけた。 結局、最終バスで上高地へ帰ることになった。若くて愛嬌のある女性運転手は髪をオシャレなアップにし、そこに帽子をちょこんとのせ、笑顔で迎えてくれたものの、上高地までの切符が見つからないらしく「さっきはここにあったのに…おかしいわ…」と独り言を言いながら首をかしげるばかりだ。とうとう手書きでバス代金を書き、それが即席の切符となった。次に、わたしたちが乗り換えるバスの運転手に上高地までの代金は支払い済みであること、バス停でわたしたちのことを待っていることを無線で連絡をしたわけだが、ちょっと遅すぎた。上高地行きのバスはすでに出発してしまったようだ。 ところがトンネルの途中で、かわいい運転手が対向車の中にわたしたちのバスを見つけ、「待て!」の合図を送った。こういうわけで、わたしたちはトンネルの真ん中で乗り換えをする羽目となり、一時的に両車線の車の流れはストップした 。バスの運転手たちは何度も「すいません」と申し訳なさそうに謝っていた。なんともスリリングなバスの乗り換えだった。 5月17日 21世紀のパーティー 今夜は地上51階の六本木ヒルズクラブで、「オラニエボール」と称するパーティーが開かれる。正式にはオランダの女王の誕生日を祝う舞踏会で、4月25日にオランダ大使が開いたレセプション(バックナンバー参照)とともに、東京における大切な行事として関東のオランダ人会によって開催される。 わたしも昔、東京でオラニエボールに何度か参加した。司会を務めたこともあっ た。ただし昔の話、だいたい昭和30年〜40年代あたり。そんなわけで、なんとなくヒルズのパーティーも華麗なるギャッツビーみたいなタキシード姿の紳士 と、イヴニングドレスをまとい煌めく宝石で着飾ったエレガントなレディがディナーテーブルで目配せしてみたり、コースの合間にパートナーを変えてクルクルと踊るような光景を想像し、彼女と一緒に互いの衣裳を入念に選び(わたしはブラックタイ、彼女はスパンコールのついたパープルのドレス)、颯爽と会場入りをした。 もしわたしが、まだ20世紀を卒業していなかったというならば、この夜に卒業し21世紀の仲間入りを果たしたわけだ。 ディナーテーブルの席順がないというより、テーブルがない。「ディナー」はバイキング形式で、食べ物は立って食べる。女性はほとんど着飾っており、半分ちかくはロングドレスで決めているのに、男性はたった2、3人だけがブラックタイ姿で、あとはビジネススーツかTシャツとジーンズ。パーティーといってもディスコみたいなもので、鼓膜が破れそうな音楽がライブバンドによって途切れなく演奏され、会話どころか色目を使うことも億劫だ。社交ダンスもエレガントにクルクルと踊るダンスもなにもない。フロアでは女性同士が踊っており、男性たちは踊りに加わることもなく、つまらなそうにフロアの外でぶらぶらしている。わたしのフォックストロットやワルツやルンバやサンバのステップはもうお呼びではないようだ。 それでもアップビートの音楽にあわせて身体をくねくね回しながらダンスを楽しんだ。 これからは「オラニエボール」という呼び方をかえたほうがいいのではないかと思う。この夜の雰囲気はどちらかというと、オランダの伝統的な田舎の「村祭り」に近いどんちゃん騒ぎのようだった。 ***4月*** 4月3日 ロンドン 自宅にもどりさっさと雑用を済ませ、いよいよ今回のお楽しみに耽るとしよう。演劇鑑賞だ。3枚のチケットは電話とインターネットで簡単に入手できた。3つの舞台はそれぞれアイリーン・アトキンズ、レイフ・ファインズ、ジェレミー・アイアンズが主役をつとめる。映画でしか見ることのない役者の演劇を生の舞台でみるなんて、わたしにとっては極上の贅沢だ。こうした贅沢はやはりロンドンならではだろう。 だからロンドンに住みたい、出かけたいと思うのだ。 4月9日 アムステルダム わたしはハーグ市生まれのアムステルダム育ちだ。両市は距離にして50キロほど離れている。 ハーグ市には中央政府があるが、首都はアムステルダム市だ。王室はハーグ市に住んでいるものの、戴冠式はアムステルダム市内の中心にある新教会で行なわれる。伝統的にアムステルダム市民は独立心が強いと言われている。反王室派もいるし、抗議デモもときどきあるが、女王の誕生日(現在はベアトリクス女王の誕生日である4月29日)にはオランダの中で一番派手に、賑やかに、どんちゃん騒ぎをする(静かさを好む市民はほとぼりが静まるまで他所へ逃げるらしい)。 外国人が混乱するのももっともだ。わたしの友人の中に教養高きイタリア人がいる。彼はオランダの首都はアムステルダムではなくハーグだと言い張る。オランダ人のわたしが違うといっても納得せず、ついに賭けようと言った。どちらが勝ったのかは言うまでもないだろう。 4月10日 アムステルダム
合理的で厳格なオランダ人でも、時には節度を失うこともあるわけだ。 4月12日 アントワープ 古い友人のアルバートが「第5回 − 紳士のための晩餐会」にわたしを招待してくれた。彼はワイン通で、そのコレクションもなかなかだ。気の合う仲間たちと一緒にワインと会話を楽しもうということで2年に一度、この晩餐会を開いている。彼自身がワインを選び、それに合う食事を作るのだ。わたしもメニューのアイデアを出し、凝ったデザインのメニューを印刷してあげる。日本からわざわざ出かけるだけの価値のある晩餐会だと言える。 4月25日 東京
オレンジ色の風船とリボンがいたる所に飾られている。オレンジはオランダ王室の色だ。子どもたちはVolendam地方の衣裳を着せられ、オランダのチーズをふるまっている。17世紀に作られた国歌も歌った。歌詞はオランダを建国したドイツ生まれのウィレム1世王子が、スペイン王に忠誠を誓いつつ、オランダの独立を守ろうと自らに言い聞かせているという、なかなか複雑な心理を反映している。今の時代にふさわしい歌詞かどうかは定かではないが、少なくともウィレム1世の理想は欧州連合というかたちで実現した(と言えるかな)! おみやげはもちろんチューリップ。オランダ産のものと思いきや、新潟からのものだった。トルコだけではなく新潟までもがオランダのチューリップに対抗しようとしているわけか…。 ***3月*** 3月17日 紳士のための仕立て屋さん 近所に「テーラーキタムラ」という店があり、よくその前を通り過ぎる。こぢんまりとした構えの店だが看板には「since1947」と記されている。 実は60年代後半か70年代前半ごろ、わたしは「キタムラテーラー」でスーツを2、3着ほどあつらえたことがあったのだが、そこの住所はこの場所ではなかったと記憶している。
店にはいると北村政彦店長が笑顔で迎えてくれた。「うちは創業以来ずっとこの場所です」と彼は言うが、わたしはこの界隈に住んだことなどないからおかしな話だ。ところが店長がわたしのジャケットのラベルを見、彼の父親が「イニシャルのHは彦吉!このジャケットは父の彦吉が作ったものだ!」と嬉しそうに言うではないか。彦吉さんとはつまり店長の祖父だ。ふたりとも喜んだだけではなく、職人として先代の技術の高さに感心していた。昔の顧客と彼らの歴史とのささやかな結びつきを記念して写真を撮った(http://www.tailor-kitamura.com参照)。 彼らは今の時代に合ったビジネスを展開しているが、それと同時に伝統を守る職人の気概を示し、それを誇りにしている。 それにしても新宿区の端に住んでいたわたしが港区三田の仕立て屋を利用していたというのはどういうわけか。わからん…。 3月24日 甘美な安堵感に酔いしれて
昨夜、昭和についての自著の原稿をアメリカの出版社の編集者に送った。執筆に2年間、推敲に2か月を費やした。この2か月間、週末休日を返上し夜も昼も机に繋がれている状態だった。睡眠と食事以外は執筆のみという生活だったと言ってもよい。気分転換に時々映画を見たり、友人と一緒にレストランや音楽会へ出かけることもあったが、リラックスなどできなかった。メインコースの最中に突然別の考えが浮かぶ。アダージョの曲にあわせて不安がよぎる。見落としている点はないか。妥当な論理か。引用は間違っていないか。 しかし今朝は微笑みを浮かべながら目を覚ました。重荷から解放されたのだ。すぐには起きず、しばらくベッドでゆっくりとした。今だかつてこのような事をしたことはなかった。遅い朝食をすませ、外出することにした。マンションのビルで出会う人たちと挨拶を交わし、隣人の子犬に話しかけると吠えられたがちっとも平気だ。鼻歌を歌いながら歩き、交通整理をしている警備員に挨拶をすると相手は驚いた表情を見せた。 長い間もだえ苦しんできた脳の細胞や回路がついに開けた、という気分だ。まるで道ぞいの桜のつぼみが開くように!東京は春たけなわだ。新しい仕事が楽しみだ。(たとえばまた本を書くとか…) 3月25日 とあるカフェの(大)宣伝
店内は席の数も少ないし、椅子の座り心地は悪い。コーヒーにはブラウンシュガーの方が合うのに、ここは白砂糖しか置いていない。他所と同じようにBGM音楽を最大ボリュームで流しており、まるでコーヒーに対抗しているようだ。 それでもこのカフェに通い続けている。ここのコーヒーを飲む時、わたしは目を閉じてこう思うのだ − ローマのヴェネト通りでコーヒーをすすっているつもりにしよう。イタリア人はコーヒー豆からエッセンスを搾り取る方法をよく心得ている。
店内のお客はたいてい一人で、コーヒーを片手に新聞を読んでいたり、静かに座 っている。わたしは最初の一口を味わった。それからカップをソーサーではなく木製らしきテーブルの上に置いた。古い習慣が身体に染み着いている、と我なが らおかしかった。陶器同士がぶつかりあう音が苦手なのだ。それよりも瀬戸物の茶わんと木製の茶托がふれあう柔らかな音のほうが好きだ。若い時に日本で発見した習慣は年をとっても忘れない。 コーヒーを飲み終え、目的地の区役所へと歩きはじめたのだが、昼食時だったの でダークスーツ姿の会社員たちが通りにあふれていた。裏道を行くとしよう。
あっと驚いた。桜が満開だ。浄土宗の寺の門の中にある木だ。わたしは立ち止まった。ブリーフケースをかかえた紳士も同じように感嘆している。「ずいぶん早いですね」とわたしが大きく呟くと、紳士は桜から目をそらすことなく「しだれ 桜ですよ」と言った。たしかに早咲きといえばしだれ桜と決まっている。 コーヒー、桜、気心の合う人との邂逅。それほど悪くもない春の始まりだ。 3月28日 さくら、さくら… 今年のお花見はどこでしましたか? わたしは増上寺で満開の桜を楽しみました。
「中国人は満開の桜を好み、日本人は散り始めの桜を好む」と言う中国人もいるようだが、少なくとも増上寺の賑わいを見る限りそのようなメランコリーはなさそうだ。芝公園でも花見の宴が盛大に行なわれており、満開の桜の美しさを心底楽しんでいる。
つまり日本人が変ったのか?内省的ではなくもっと人生をおう歌するようになっ たのだろうか?人生の頂点は何回でも繰り返しが可能と考えるようになったのか?なるほど一理ある。世界一の長寿国を誇る今の日本では、命の短さを憂えるこ とが昔ほどなくなったのかもしれない。 2月9日 NHKホールでのコンサート 7時からのコンサートには十分間に合う時間に会場のNHKホールへ到着。まずはチケットを受取り、近所のカフェか会場内のどこかで軽食をすませ、それから演奏を楽しむとしよう。今夜のプログラムはチョン・ミョンフン指揮によるブルックナーの交響曲第7番ホ長調。その前にメシアンが予定されている。 それにしてもロビーは無気味なほど閑散としている。6時をちょっと過ぎたところなので、おそらくまだどこかで食事をしている人が大半なのだろう。わたしたちもホール内の売店でサンドイッチとグラスワインをもとめ、テーブルについた。やはり日本だ。椅子が低すぎる。まるで子どもサイズだ。片隅に設置されているテレビの画面を見ると、どこかのコンサートがうつしだされている。早々と会場に到着したわたしたちのような観客のために用意されたものだ。気がきいている。でもわたしは演奏にそなえパンフレットを読むことにした。 6時半をまわったころドアが開き、大勢の人たちが出てきた。「演奏前のトークかなにかが終わったのかな」とわたしは友人へ言った。ドリンクを手にテーブルに座る人、パンフレットを読む人、腕時計に目をやる人たちに囲まれ、わたしたちは残りのサンドイッチをほおばった。ヨーロッパのコンサート会場にありがちなざわめきやおしゃべりが皆無だ。友人いわく、日本では社交場としてのコンサートの雰囲気を楽しむというより音楽を聴きにくるからだ。つまり日本人は真面目なのだな。 突然、わたしたちは気がついた。これは休憩時間なのだ!不覚にも前半を聞き逃してしまった。チケットを確認すると確かに6時開演と印刷されている。通常7時開演のNHKらしからぬ時間だ。 それにしてもチケットを受け取った時にも、会場に入った時にも誰もわたしたちに演奏がはじまっていることを知らせてくれる人はいなかった。知らぬが仏とはこういうことか。でも、知っていたらせめてメシアンの演奏をテレビ中継で見ることができたのに…。 それでもブルックナーの演奏を聴けただけでも十分満足だった。 2月10日 雪景色の東京 地球温暖化が懸念される今日この頃。それでも東京に雪が降り、ようやく冬が来たという気分だ。なんでも東京は1876年以来、雪の降らない冬はなかったようだが、最近の傾向としてはスノーブーツを探している間に雪がとけてしまう。
今日の雪もわたしがカメラを探している間にとけてなくなってしまった。そこで昭和36年の雪景色をお見せします。 昔の雪は止むことなく降りつづけたので、文机にむかい墨と筆と和紙を広げ俳句のひとつでもひねってみることもできた。 芭蕉(1644−1694)は繊細で本物の雪をわかっていたようだ。さすがである。 初雪や水仙の葉のたわむまで (英訳) 北の地方では今でも冬となれば大雪といったところでしょう。そうした雪景色をとらえたのが内藤丈草(1662−1704)。 野も山も雪にとられて何もなし (英訳) (英訳はR.H. Blythによる) 積雪量が減少の傾向にあるのは日本の都市部のみとはかぎらない。世界の温帯地域全体で起きているようだ。
これは昭和36年に撮影したもの。オランダの郊外にあったわたしの両親の家の前の雪景色だが、いまではこのような光景はほとんど見られない。 2月16日 東京で見つけた王妃のチョコ 六本木ヒルズができてから麻布十番界隈に活気がでてきた。ブティック、レストラン、カフェばかりではなく、数年前には見かけなかったような店まである。 今日は「ア ラ レーヌ アストリッド (A la Reine Astrid)」というチョコレートショップを偶然見つけた。スウェーデン出身のベルギー王妃アストリッドにちなんで名づけられたお店だという。この美しく人々から愛された王妃が1935年に自動車事故で亡くなった時の悲しみはベルギーだけにとどまらなかった。それにしても、この店はパリにあるという。謎を解くためドアを開けてたずねてみた。 1935年、創業者のフェルナンデ ゴベールは亡くなった王妃の名前をパリに新しくオープンする自分の店の名として使用することをベルギー王室より許可されたという。パリにある本店は写真で見るかぎり、とてもこぢんまりとしているが、それでも東京のおしゃれな界隈に進出できるほどに成功しているようだ。こうしてみると東京もスタイルとテイストに関しては世界の中心といえよう。
店内でアルバムを見せてもらった。アストリッド王妃の短くも華やかな人生を物語るカラー付き‘ファンカード’(絵はがきのようなカード)のコレクションが貼ってある。 そういえば母は王妃の死に大変ショックをうけていたなあ。彼女の死は1997年に起きたダイアナ妃の事故死と同じほどの動揺をもたらしたといえるかもしれない。 2月23日 銀座での買い物中に思ったこと 寒いような暖かいような東京の冬にも防寒用の下着はかかせない。そこで股引を買いにでかけた。ところがお上品なデパートの下着売り場で聞いてみたところ、女子店員は「もも…?」と言いかけて男子店員の助けを求めた。「あ!ロングパンツのことですか」「今はそう言うの」とわたしはたずねた。というのは、彼の「ロング」という発音が「長い」ロングではなく「まちがった」ロングに聞こえたので、ほんとうにお互いが同じ下着を話題にしているのかどうか不明だったからだ。彼は微笑み、ちょっと頭を下げた。ここの店員はこういう時「はい、わたくしども氷河時代からそのように呼んでおります」などと言わぬように教育されている。 このやりとりを見ていた翻訳家の溝口さんは、わたしが使った「股引」は正しい日本語だが古くさい感じがするので、最近は英語をカタカナ化した言葉を使うようになってきているのだと教えてくれた。例えば、りんご、ぶどう、いちごはアップル、グレープ、ストロベリー。下着はインナーウェアで靴下もいつの間にかソックスだ。日本のアベックは接吻ではなくキスをし、サラリーマンは解雇されるのではなくリストラされるという。そのうち「日本」も「股引」のように忘れ去られ、「ジャパン」となる日がくるのだろうか。 ***1月*** 12月31日 東京 午後7時 ひっそりと静まりかえった都内の某病院。あちらの4人部屋やこちらの個人病室から薄暗い明かりがもれている。退院できない患者がとり残されているようだ。7階のフロアには夜勤の看護婦がたった一人。 他の患者はどこにいるのか?なぜ大晦日の夜に手術をするのはわたし一人だけなのか?急性盲腸炎の人はいないのだろうか?正月休みの4日間が終わるまで待てない急病人はいないというのか? わたしの急性盲腸炎を診断した外科医は大晦日の手術を躊躇した。こらえきれぬ痛みのために悲鳴をあげているわたしの症状を疑っていたからではなく、正月休みがはじまった矢先、人手を召集しなければならないからだろう。外科医の提案はこうだった。一時的に薬で痛みをちらし、言うことを聞かないこの無駄な臓器がメスを入れることなくおとなしくなるかどうか様子を見てみるとしよう。 実のところこれで盲腸炎がおさまるなど彼は信じていなかったし、わたしもそんな姑息な手にだまされはしない。外科医はただ、これからかけなくてはならない召集の電話は自分のせいではなく、患者のわたしのせいであることをはっきりさせたかったのだろう。わかった。手術だ。ただちに手術をしてこの痛みを止めてくれ。わたしは彼に命じた。付き添いの友人(彼女自身も医者)もそれがいいと首を縦にふった。さっそく同意書やら免責条項やらにサインをし、手術決行の運びとなった。 つまり無鉄砲にならなくてはいけない時もあるわけだ。 車椅子にのせられ手術室に入ってみると、わりと若い外科医であることがわかった。たぶんまだ若いから手術を躊躇したのかもしれない。経験も浅いことだろう。痛みに苦しみながら、やはり手術はやめるべきかと考え直したが、すでに麻酔医はスタンバイ状態に入っていた。ニヤリとした表情をうかべる彼を見た時「もう後にはもどれない」と観念した。 午後10時 わたしの名前を呼ぶ声がどこか上の方から聞こえてくる。目を開けるといくつかのゆがんだ顔が、まるで乱雲のようにおおいかぶさっている。よく見ると外科医と看護婦たちだった。声をそろえて「手術は終わりました」と言われ、驚きと安堵の笑みをなんとか浮かべる。 今夜だけは集中治療室で過ごすこととなった。夜勤の看護婦はわたしのことを新生児のように扱う。これからの12時間、この看護婦がお母さん代わりということか。ただしわたしの場合は、術後の身体の経過を見るためにここにいるわけだ。彼女はじゅうぶんなほど気を配り、わたしから目を離さない。いつの間に眠ってしまったのは、おそらく意識の辺境に残された麻酔薬のせいかもしれない。 年が明けて2008年の元旦 正午 意識はすっかり回復し、車椅子で7階へ移動。身体にはまだチューブや点滴がついたままだが、気分は良い。検査のためにかわるがわるやって来る看護婦たちは、患者であるわたしの尊厳を尊重してくれる。笑顔や冗談や励ましの言葉などが抗生物質や点滴と見事に混ぜ合ってわたしの身体に注入される。 どうやら世間ではゆっくりと元旦の朝を迎えているようだ。雲ひとつない青空。気温は10度。きっとどこの家庭でもおせち料理を囲みながら、漆塗りの盃でお屠蘇を飲んでいるにちがいない。正月三が日は会社も工場もすべて休みだ。バスや電車の運転手や病院のスタッフといった特別な職業についている人だけが休まず働いているのだろう。神社や寺院は着物姿の参拝客でにぎわっているにちがいない。 満足感が身体中に広がる。病院にいてよかった。 1月4日 午前11時 正月休みは終わった。病院もしかり。我慢できる程度の軽い病気にかかった患者たちはタイミングよく戻ってくるし、中断していた治療も再開だ。病室のベッドも空きがなくなり、手術室もランプがつきっぱなしの状態。 それでも院内は整然としており清潔で明るい。スタッフも看護婦たちも礼儀正しい。病院の建物もしゃれたデザインだ。軽快に踊る娘たちと無垢な鳩を描いた牧歌的な絵がひろびろとしたロビーの壁面に飾ってある。看護婦たちは落ち着いて小走りに移動し、時には笑顔やおじぎさえしてくれる。ドアを乱暴に開ける人や大声でどなる人などいない。それでいてわざとらしいところがない。まったく自然な所作なのだ。 衛生度はたいへんよろしい。床は定期的にモップがかけられ、鏡についている汚れもすぐに拭き取られる。病院の裏や従業員専用のエレベーターも清潔だ。ロンドンの病院で見た光景とはまったく正反対だ。 また、ヨーロッパの病院や診療所で嗅ぐ消毒薬の臭いがしない。病院にいるというよりも回復目的のリゾート施設のようだ。ハブリヘルスセンターとでも呼ぼうか! 午後3時 体温と血圧を計っている看護婦から日本での暮らしは楽ですかと聞かれ、どう答えていいのかわからずベテラン弁護士の口癖のように「そうですね、ある意味では楽ですが、その反面…」と言いかけたが、看護婦はそれに対してはなにも言わない。 そうか、日本の文化とか社会うんぬんではなく、おそらくここがいいのかそれともわたしがやって来たあちらの国がいいのか、ということを知りたいのだな。「まあそうですね」と言いながら、わたしの腕から血圧計をはずし「130の85。悪くありません。よく思うんです、アメリカ人にとってここでの暮らしは不便じゃないかってね」「わたしはオランダ人です」ちょっとこだわって言ってみた(わたしのことをアメリカ人と間違うと、相手の日本人は恥じ入って謝るのだが、いつもわたしは知らん顔をする)。 「日本での暮らしは楽ですよ、本当です。電車も地下鉄もきれいだし、時刻表どおりに運行します。道路は安全だし清掃がゆきとどいています。コンビニストアーはありがたいし、宅急便なんてオランダにはないです。宅急便なしでどうやって暮らしているのだろうと思うほどです。駅にはエスカレーターとエレベーターの両方があるでしょ。ロンドンでは階段を使うんですよ。ここでは食べ物もバラエティーに富んでいるし、本当に日本での暮らしは楽です。それに…」「そうですか」そういって首をかしげ、腕時計に目をやった。「もう行かなくちゃ。また後でうかがいます」そう言って微笑んだ。旅行ガイドにはロンドンやパリやアムステルダムですら「魅力あふれる」都市と紹介されているのだろうが、そこでの生活の不便さについてはいっさい触れていないものなのだ。 別の看護婦はわたしの「美しい英語」をほめてくれた(でもわたしは彼女には日本語しか話さなかったと思うのだが…)。どうやらわたしが友人と英語で話しているのをたまたま聞いていたようだ。「アメリカンイングリッシュではなくクイーンズイングリッシュですね!」と言われると、こちらとしてはちょっとアメリカ人が気の毒に思えてくる。日本の政治、経済、文化に半世紀近く深くかかわってきたにもかかわらず、アメリカ人の英語は日本ではいまだに“それなりの評価”を得ていないということなのか。 1月9日 まだ入院中。オランダ人、イギリス人、アメリカ人の友人たちはこれが自分たちの国だったらとっくに退院しているはずだ。いや、そもそも休暇中に入院できるかどうかもわからないと驚く。「びっこをひいていようが、すこしでも歩けるとわかったら退院さ!」なるほど。 でも日本では話は別だ。健康管理に関しては慎重だ。病院にとどめておく理由が尽きるまで、日本では退院させてもらえない。しかも国民保険という素晴らしい制度のおかげで医療費が全額請求される心配もない。 そんなわたしもいよいよ明日退院だ。担当の外科医はこれ以上わたしを入院させておく必要がないと判断なさった。さっそく病院内のカフェでケーキと紅茶でお祝いをするとしよう。それにしても、季節はずれの綿の浴衣姿で歩くわたしを見ると大半の女性は微笑みを投げかけ、男性はいぶかしげな眼差しを注ぐのはどうしてだろうか。 途中で6階に立ちよった。去年このフロアの看護婦たちにはいろいろとお世話になったからだ。驚いたことに誰もがすぐにわたしのことを思い出し、笑顔で迎えてくれた。「どうしてここにいるのですか?」と聞かれ「急性盲腸炎、手術しました、大晦日にね」と答えると、一斉に大笑い。日本人はユーモアのセンスに欠けるというけど、そうとはかぎらない!もっとも、75歳になっても盲腸があるのはおかしかろうし、大晦日にその手術をしたというのだからなお愉快であることは確かだが。 日本がいいか、よその国がいいかなどと考えたりせず、この時だけはただ楽しいひとときを満喫。 
1月22日 「入院生活を楽しんだ」という誤解を与えないように付け加えておきたい。もしなんらかの病気で入院しなければならないとしたら、日本にある病院のほうがいい。それだけの事。その理由はすでに述べたとおりである。 退院してからはデスクワーク中心の日々を送っているが、今日は名古屋へ日帰りで出張をすることになった。このハブリ日記を含むわたしのウェブサイトの翻訳を担当している溝口さんも同行してくれる。 ところが、名古屋のタクシーの運転手のおかげで“ありきたり”とは言えぬ出張となった。 以前から名古屋のタクシーの運転手はおしゃべりだと感じていたが、今回もご多分に洩れずよくしゃべる人だ。行き先を告げ、車が走り出し、数分もたたぬうちに彼のおしゃべりがはじまった。九州出身であること、自分の会社の4分の3は九州出身だ、かつて年配の男性客を福岡まで連れて行った、先祖の墓参りをしたいし、年をとってきたので死ぬ前に開通したばかりの高速道路で九州まで行ってみたい、こちらが20万円、片道で、と言ったら彼は承知した、お墓に到着し線香を供えたら今度は名古屋へ引き返してくれと言うので今度は10万円ということになった、20年前の話だったが、今でもその男性は近所に住んでいて果物などを持って行く。 これには大笑いした。溝口さんが「でもそんなことはめったにないでしょ」と言うと、運転手は「鳥取にも行きましたよ、14万円でした。東京までも何度か行きました。毎晩名古屋から大阪や京都やいろいろな所へ行くお客さんが必ずいるんです。」「でも、新幹線の方がずっと速いのに」とわたしが言うと、「新幹線は夜は走らないでしょ。わたしのお客さんは夜中に行きたい人たちなんですよ。親の死に際にかけつけるとか、家族が事故にあったから家に帰りたいとか…。この間は馬券で100万円儲かった、急に栃木の両親に会いに行きたいというお客がいました。夢に番号がでてきて、その通りの馬券を買ったら当たったと言ってました」 話はつきないようだったが、やれやれようやく目的地に到着した。タクシー代は3200円也。30分間のおしゃべり付きだから悪くはなかろう。 |
 期待は裏切られることなく、力みなぎる印象的なコンサートだった。カラファックスは実はジャズバンドではなく正当なクラシック演奏家で、過去20年間に23カ国でクラシックとジャズの両方を演奏してきた実績ある楽団だ。今回は彼らにとって初来日となる。
期待は裏切られることなく、力みなぎる印象的なコンサートだった。カラファックスは実はジャズバンドではなく正当なクラシック演奏家で、過去20年間に23カ国でクラシックとジャズの両方を演奏してきた実績ある楽団だ。今回は彼らにとって初来日となる。 慶応義塾大学の創立150年を祝い記念切手が発売された。三田キャンパスにあるゴチック様式の図書館(旧館)や福沢諭吉、慶応には欠かせないラグビーや野球のイラストも印刷されている。
慶応義塾大学の創立150年を祝い記念切手が発売された。三田キャンパスにあるゴチック様式の図書館(旧館)や福沢諭吉、慶応には欠かせないラグビーや野球のイラストも印刷されている。 日本の技術はとにかく素晴らしい。壁画をはずし、しばらくしてから元に戻すことができる国が日本以外にあるというのか。納得することにした。時にはただ驚くだけという方が良い時もある。
日本の技術はとにかく素晴らしい。壁画をはずし、しばらくしてから元に戻すことができる国が日本以外にあるというのか。納得することにした。時にはただ驚くだけという方が良い時もある。





 前回はイギリス人の書いた明治時代のハガキを紹介した。今回は日本人のハガキを紹介する。
前回はイギリス人の書いた明治時代のハガキを紹介した。今回は日本人のハガキを紹介する。 次に紹介するのは明治39年10月25日付で、宛名は東京の幸田方(下宿)横浜勉様となっている。
次に紹介するのは明治39年10月25日付で、宛名は東京の幸田方(下宿)横浜勉様となっている。 たとえばこのハガキは1905年4月17日にミドルセックスから投函されたものだ。切手は半ペニー、宛先はケント州のフォークストンに住むG. ヴェニング嬢。
たとえばこのハガキは1905年4月17日にミドルセックスから投函されたものだ。切手は半ペニー、宛先はケント州のフォークストンに住むG. ヴェニング嬢。 4銭の切手が貼ってあるこのハガキは西洋式に「1907年8月23日神戸」と記され、宛先はイングランドのG. ディクソン嬢(Dickson)。差し出し人はGD。宛名と同じイニシャルだ。内容はちょっとお固い。
4銭の切手が貼ってあるこのハガキは西洋式に「1907年8月23日神戸」と記され、宛先はイングランドのG. ディクソン嬢(Dickson)。差し出し人はGD。宛名と同じイニシャルだ。内容はちょっとお固い。
 努力は実った。写真展は想像以上に素晴らしいものとなった。額装された115点の写真と、入口付近に掲げたパネルに使用した20点あまりの写真が、フジフイルムスクエアのギャラリーに展示された。
努力は実った。写真展は想像以上に素晴らしいものとなった。額装された115点の写真と、入口付近に掲げたパネルに使用した20点あまりの写真が、フジフイルムスクエアのギャラリーに展示された。 28日の夜に内覧会をかねたパーティーが開催された。オランダ大使と日蘭協会の会長でもある富士フイルムの古森社長も同席し、会場には100人以上ものゲストと20人近くのマスコミが集まった。
28日の夜に内覧会をかねたパーティーが開催された。オランダ大使と日蘭協会の会長でもある富士フイルムの古森社長も同席し、会場には100人以上ものゲストと20人近くのマスコミが集まった。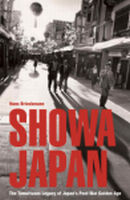 Showa Japan: the Post-War Golden Age and its troubled legacyというわたしの本がついに出版された。偶然にも都内で開催中の写真展「あるオランダ人が見た昭和の日々」と重なった。米国のタトル出版社は英語圏での販売のみならず、日本の書店やインターネットでも購入できるように手配をしてくれた。(Tuttlepublishing.comもしくはAmazon.comで上記のタイトルを入力してみてください。)
Showa Japan: the Post-War Golden Age and its troubled legacyというわたしの本がついに出版された。偶然にも都内で開催中の写真展「あるオランダ人が見た昭和の日々」と重なった。米国のタトル出版社は英語圏での販売のみならず、日本の書店やインターネットでも購入できるように手配をしてくれた。(Tuttlepublishing.comもしくはAmazon.comで上記のタイトルを入力してみてください。) 写真展の最終日がきた。一ヶ月間の開催中に4万8千人以上の来場者が、わたしと友人ロッへの写真を見てくれたという。もっと見たいという要望もたくさん寄せられた。日本だけではなく欧米でも展示をしてほしいという声もあがった。
写真展の最終日がきた。一ヶ月間の開催中に4万8千人以上の来場者が、わたしと友人ロッへの写真を見てくれたという。もっと見たいという要望もたくさん寄せられた。日本だけではなく欧米でも展示をしてほしいという声もあがった。
 最近はロンドンの国際都市度も急上昇中といえるだろう。昔からイギリス人を見下していたフランス人でさえ、今では30万人以上のフランス人がロンドンで暮らしているらしい。おかげでロンドンはパリ、リヨン、ニースに次ぐ4番目に大きな「フランス人都市」となっている。
最近はロンドンの国際都市度も急上昇中といえるだろう。昔からイギリス人を見下していたフランス人でさえ、今では30万人以上のフランス人がロンドンで暮らしているらしい。おかげでロンドンはパリ、リヨン、ニースに次ぐ4番目に大きな「フランス人都市」となっている。 国際都市という点ではロンドンと引けを取らないアムステルダム。ロンドンほどの規模と洗練さはないが、それでも負けないものがある。街を縦横につなぐ運河だ。旅行者向けの運河ツアーもあるが、今日は私の甥が彼の所有するボートに招待してくれた。シャンペンを飲みながら、運河沿いに並ぶ17世紀から19世紀の歴史的邸宅を見ているうち、ほろ酔い気分になってきた。
国際都市という点ではロンドンと引けを取らないアムステルダム。ロンドンほどの規模と洗練さはないが、それでも負けないものがある。街を縦横につなぐ運河だ。旅行者向けの運河ツアーもあるが、今日は私の甥が彼の所有するボートに招待してくれた。シャンペンを飲みながら、運河沿いに並ぶ17世紀から19世紀の歴史的邸宅を見ているうち、ほろ酔い気分になってきた。 すると、カイツブリの親子を発見。たくさんのボートが行き来する運河の片隅に、うまいこと巣を作って暮らしているようだ。ボートを近づけスナップ写真を撮った。この写真では明瞭ではないが、親鳥のそばに2羽のヒナ鳥がいて、一羽は親にくっついて泳いでいたが、もう一羽は親鳥の背中にちょこんと乗っていた。
すると、カイツブリの親子を発見。たくさんのボートが行き来する運河の片隅に、うまいこと巣を作って暮らしているようだ。ボートを近づけスナップ写真を撮った。この写真では明瞭ではないが、親鳥のそばに2羽のヒナ鳥がいて、一羽は親にくっついて泳いでいたが、もう一羽は親鳥の背中にちょこんと乗っていた。 創業100周年を祝う老舗のリゾートホテルは、一貫して家族経営を貫いており、どこのブランドホテルにも属さない。それでも客をひきつける魅力がある。それは彼ら独自のサービスだ。
創業100周年を祝う老舗のリゾートホテルは、一貫して家族経営を貫いており、どこのブランドホテルにも属さない。それでも客をひきつける魅力がある。それは彼ら独自のサービスだ。 その3 日本のスーパーや店は、誰もいない場合でも、商品広告のラジカセや小型ビデオTVを流しっぱなしにしている。
その3 日本のスーパーや店は、誰もいない場合でも、商品広告のラジカセや小型ビデオTVを流しっぱなしにしている。 今年のテーマはシューベルトだった。400近くの演奏会が、世界各国から集ま った1700人以上の演奏者たちによって実現した(国際フォーラムの中庭の木陰で行なわれた無料コンサートも含む)。
今年のテーマはシューベルトだった。400近くの演奏会が、世界各国から集ま った1700人以上の演奏者たちによって実現した(国際フォーラムの中庭の木陰で行なわれた無料コンサートも含む)。 と、思ったら「カフェプレイエル」という看板が目にはいった。時間をつぶすに はちょうどいい。いや、電車とバスの乗り換えの待ち時間のためにあるカフェなのかもしれない。中に入るとどことなく1950年代頃のヨーロッパのような昭和のような雰囲気が懐かしい、素敵なカフェだということがわかった。店内には 地元のアーチストたちの作品が飾られ、プレイエル・ピアノがさりげなく置いてあり、美しいハープシコードがカフェに隣接したギャラリー部屋に展示されているではないか。しかもこのハープシコードは地元の楽器職人の手によって作られたものだという。カフェのオーナー自身も音楽家だ。品のあるご婦人で、絵柄の美しい磁器でいただいた煎れたてのコーヒーは実においしかった。
と、思ったら「カフェプレイエル」という看板が目にはいった。時間をつぶすに はちょうどいい。いや、電車とバスの乗り換えの待ち時間のためにあるカフェなのかもしれない。中に入るとどことなく1950年代頃のヨーロッパのような昭和のような雰囲気が懐かしい、素敵なカフェだということがわかった。店内には 地元のアーチストたちの作品が飾られ、プレイエル・ピアノがさりげなく置いてあり、美しいハープシコードがカフェに隣接したギャラリー部屋に展示されているではないか。しかもこのハープシコードは地元の楽器職人の手によって作られたものだという。カフェのオーナー自身も音楽家だ。品のあるご婦人で、絵柄の美しい磁器でいただいた煎れたてのコーヒーは実においしかった。 散歩日和。アムステルダムにも春がやってきた。陰気な冬が終わり、太陽に飢えた人々はいっせいにカフェやビストロのテラスで食事やおしゃべりを楽しもうとしているものだからどこに行っても満席状態。しかたがない。運河沿いに建っている、17世紀から18世紀の豪商たちの家々を鑑賞しながら歩くとしよう。豪華な造りのものもあるが、控えめなものが多い。富を見せびらかすのはよくないというのが従来のオランダ人の考え方だ。
散歩日和。アムステルダムにも春がやってきた。陰気な冬が終わり、太陽に飢えた人々はいっせいにカフェやビストロのテラスで食事やおしゃべりを楽しもうとしているものだからどこに行っても満席状態。しかたがない。運河沿いに建っている、17世紀から18世紀の豪商たちの家々を鑑賞しながら歩くとしよう。豪華な造りのものもあるが、控えめなものが多い。富を見せびらかすのはよくないというのが従来のオランダ人の考え方だ。 花で飾り立てられた自転車を見つけた。オランダといえば花。とくにチューリップは特別だ。もともとは中央アジアの野生の花で、最初はトルコで栽培された。しかし17世紀にオランダで交配が重ねられ、さまざまな形と色のチューリップが生まれた。これがいわゆるTulipmania(チューリップマニア)と呼ばれる、いわば投機ブームのひきがねとなったわけだ。新種の球根ひとつが一軒の家の値段にまでつり上がったそうだ。まるで80年代の日本のバブル経済のようだ。
花で飾り立てられた自転車を見つけた。オランダといえば花。とくにチューリップは特別だ。もともとは中央アジアの野生の花で、最初はトルコで栽培された。しかし17世紀にオランダで交配が重ねられ、さまざまな形と色のチューリップが生まれた。これがいわゆるTulipmania(チューリップマニア)と呼ばれる、いわば投機ブームのひきがねとなったわけだ。新種の球根ひとつが一軒の家の値段にまでつり上がったそうだ。まるで80年代の日本のバブル経済のようだ。 ベアトリクス女王の誕生日を祝うレセプションがオランダ大使の自宅で行なわれる。関東一円に住んでいるオランダ人たちが招待された。わたしもその一人。さっそく東京タワーのそばにある大使宅へ出かけることにした。昭和初期の洋館は品格にあふれている。天気が良かったのでガーデンパーティーとなった。つつじや芍薬やチューリップが満開だ。
ベアトリクス女王の誕生日を祝うレセプションがオランダ大使の自宅で行なわれる。関東一円に住んでいるオランダ人たちが招待された。わたしもその一人。さっそく東京タワーのそばにある大使宅へ出かけることにした。昭和初期の洋館は品格にあふれている。天気が良かったのでガーデンパーティーとなった。つつじや芍薬やチューリップが満開だ。 そこでH.Kitamuraというラベルのついた古いジャケット(写真参照)を持ってその店に立ちよってみることにした。義母の手織りによる生地は丈夫なうえ、年月がたってもまったく傷むことなく風合いも失われていない。今でも冬のジャケットとして愛用している。
そこでH.Kitamuraというラベルのついた古いジャケット(写真参照)を持ってその店に立ちよってみることにした。義母の手織りによる生地は丈夫なうえ、年月がたってもまったく傷むことなく風合いも失われていない。今でも冬のジャケットとして愛用している。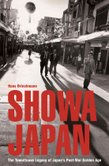
 東京ならおいしいコーヒーが飲める場所を探すために、あちこち歩きまわる必要 などないはずだ。ドトール、スターバックス、キーコーヒー等々街はカフェであふれている。わたしも大小いろいろと通ったが、結局Segafredoという所が気に入った。ただしチェーン店であるにもかかわらず店舗数は少なく、どちらかというと不便な場所にあるので、一杯のカプチーノを味わう楽しみのためにわざわざ用事を見つけてカフェのある方角へ出かけていかなくてはならない。
東京ならおいしいコーヒーが飲める場所を探すために、あちこち歩きまわる必要 などないはずだ。ドトール、スターバックス、キーコーヒー等々街はカフェであふれている。わたしも大小いろいろと通ったが、結局Segafredoという所が気に入った。ただしチェーン店であるにもかかわらず店舗数は少なく、どちらかというと不便な場所にあるので、一杯のカプチーノを味わう楽しみのためにわざわざ用事を見つけてカフェのある方角へ出かけていかなくてはならない。 この日は浜松町の貿易センタービル内にあるSegafredoに立ちよった。昼食前だっ たのでカプチーノのグランデ(大)を注文。エスプレッソは食事の後に飲むものなのだ。イタリア人やフランス人は食事の後にミルク入りコーヒーを飲まない。消化に悪いからだ。
この日は浜松町の貿易センタービル内にあるSegafredoに立ちよった。昼食前だっ たのでカプチーノのグランデ(大)を注文。エスプレッソは食事の後に飲むものなのだ。イタリア人やフランス人は食事の後にミルク入りコーヒーを飲まない。消化に悪いからだ。
 一夜明けたら一斉に開花したという具合で、花見客が大勢集まり、桜の木に隠れるように立っている観音様もこの様子に浮かれているようだ。
一夜明けたら一斉に開花したという具合で、花見客が大勢集まり、桜の木に隠れるように立っている観音様もこの様子に浮かれているようだ。


